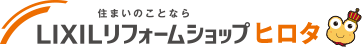外壁塗装
外壁シーリングの耐用年数は約10年!劣化のサインと費用相場を解説
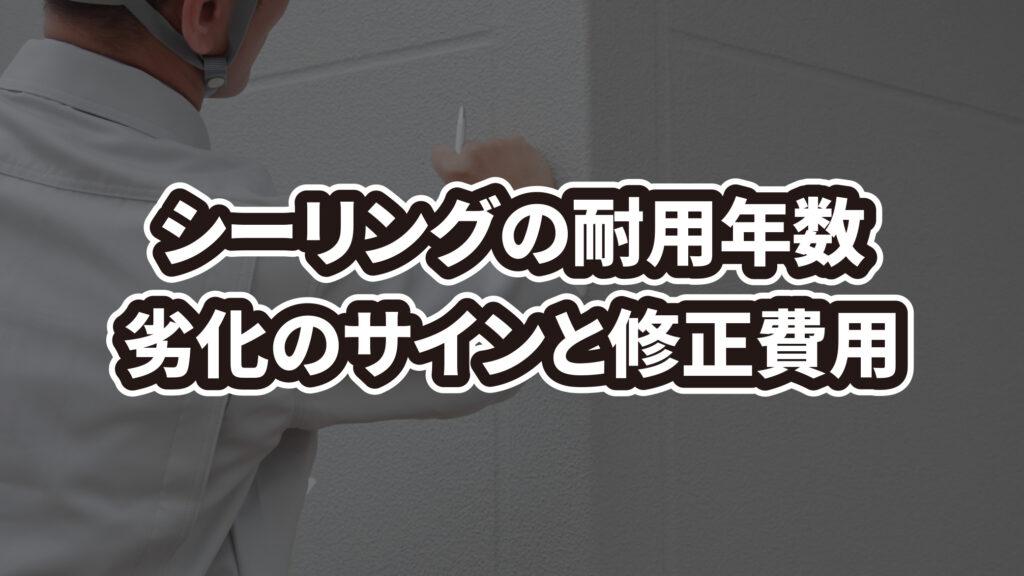
「シーリングの耐用年数を知りたい」
「いつ補修したらいいのかわからない...」
「費用はどのくらいかかるの?」
あなたはこのような悩みをお持ちではないでしょうか?
外壁のシーリングは、外壁の隙間や継ぎ目を密閉する役割があり、雨水の浸入を防いでくれます。継ぎ目を整えられるので、住宅の美観維持にも繋がります。外壁に使用されるシーリングの耐用年数は約10年程度で、劣化が始まると、ひび割れや剥がれ、変色などの症状が現れます。劣化を放置すると雨漏りに繋がり、被害がさらに拡大する恐れがあります。大切な住まいを守るためにも、シーリングの劣化を見つけたら早めの補修が欠かせません。
ですが、「劣化がどの程度進んでいるのかわからない」「メンテナンスのタイミングがわからない」という方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、シーリングの劣化が気になっている方に向けて、劣化のサインや補修費用の相場、補修時期の見極め方について詳しく解説していきます。
外壁シーリングの耐用年数は約10年程度
外壁に使われるシーリングの耐用年数は、使用するシーリングの種類によって異なりますが、一般的な目安は10年程度になります。また、日差しが強かったり、寒暖差が大きかったりすると、耐用年数よりも劣化が早く進むこともあります。劣化の症状をいち早く見つけるためには、定期的なメンテナンスが必要です。住宅の環境にあわせたシーリング選びも重要になります。
種類ごとの耐用年数の違い
外壁シーリングの耐用年数は、約10年が一般的ですが、使用するシーリングによって、耐用年数は異なります。シーリングの種類ごとの耐用年数は、主に以下のとおりです。
| シーリングの種類 | 耐用年数 |
| アクリル系 | 約5~7年 |
| ウレタン系 | 約5~10年 |
| ポリウレタン系 | 約5~10年 |
| シリコン系 | 約10年 |
| 変性シリコン系 | 約10~15年 |
シーリングの寿命は10年程度が目安になるため、15年以内には補修を検討するとよいでしょう。
ですが、耐用年数よりも劣化が早く進んでいる可能性もあります。そのため、シーリングの劣化が進んでいないか、定期的に目視での確認も必要です。もし劣化が進んでいたら放置せず、劣化の進行を防ぐために、早めの対策を行いましょう。
環境条件が耐用年数に与える影響
シーリングは住宅の周辺環境によっては、耐用年数より短い期間で、劣化が早く発生する場合があります。劣化を早める原因は、主に以下のとおりになります。
- 紫外線
- 雨風
- 温度変化
- 施工不良
- シーリングの選定ミス
シーリングは種類によって、使用に適した場所や性能が異なります。たとえば、紫外線に弱かったり、湿気や気温変化に対応できないシーリングだったりすると、耐用年数より短い期間で寿命を迎えます。そのため、周辺環境を考慮したシーリング選びが重要です。
耐用年数を延ばすためのポイント
シーリングの耐用年数を延ばすためのポイントは、以下の3つになります。
- 紫外線や雨風に強いシーリングを選ぶ
- 住宅環境にあったシーリングを使用する
- 専門業者に点検を依頼する
紫外線や雨風に強いシーリングを選ぶ
紫外線や雨風はシーリングを劣化させる原因となりやすいため、耐候性に優れたシーリングを選ぶようにしましょう。予算によっては、紫外線に強いシーリングが選べない方もいらっしゃると思います。紫外線に弱いシーリングの場合は、上からの塗装で長持ちさせることもできます。
住宅環境にあったシーリングを使用する
住宅によっては、風が強い地域だったり、寒冷地だったりと周辺環境は様々です。住宅環境にあわせたシーリングを選ばないと、劣化が早まり、ひび割れや剥がれが発生しやすくなります。
たとえば、海沿いに面している住宅では塩害のリスクも考えて、耐候性の強いシーリングを選ぶと良いでしょう。耐候性や防水性に優れているシーリングを選べば、どんな環境にも適応しやすいため、耐用年数を延ばすことに繋がります。
専門業者に点検を依頼する
ご自身でシーリングの状況を確認することも大切ですが、専門業者への点検も検討してみましょう。なぜなら、素人では判断が難しい劣化をプロの目で見つけることができるからです。見た目では問題なくても、内部でシーリングが剥がれている可能性もあります。劣化の初期段階で発見できれば、シーリングの劣化を未然に防げるでしょう。
業者によっては、劣化の状況に合わせて補修方法や補修のタイミングに関するアドバイスをしてもらえます。点検を無料で行ってくれる業者もあるため、シーリングの劣化が気になる方は、無料点検から始めてみましょう。
外壁に使われるシーリングの役割と重要性
シーリングとは、外壁材の継ぎ目や隙間を埋めるためのゴムような素材のことです。外壁だけでなく、屋根の継ぎ目やベランダ、バルコニーの防水部分など幅広く使われています。雨水の浸入を防ぐだけでなく、クッションのような役割もあり、建物の動きに追従し衝撃を吸収してくれます。
常に紫外線や雨風を受けるため、劣化の進みやすい箇所でもあり、劣化をいち早く見つけることが重要です。
シーリングは外壁材の継ぎ目や隙間を埋める役割がある
シーリングには雨水や湿気、空気の浸入を防ぐ役割があり、防水性と気密性を確保することができます。外壁以外にも、以下の箇所でシーリングは使われています。
- 窓ガラスとサッシの間
- 屋根の継ぎ目
- ベランダやバルコニーの防水部分
- 浴室やキッチンのスキマ
- エアコンの配管周り
窓や屋根、ベランダやバルコニーなど幅広く使えるのが、シーリングの特徴です。
外壁のひび割れを防いでくれる
シーリングは防水性や気密性を高めるだけでなく、柔軟性もあるため、外壁のひび割れを予防に役立ちます。なぜなら、シーリングは建物のわずかな動きに追従して、動きを吸収してくれるからです。
建物は温度変化や地震などの揺れで、常に少しずつ動いています。硬い外壁材を使用している場合は、建物の動きに追従できず、ひび割れが発生しやすくなります。ひび割れが発生すると、その隙間から雨水が浸入しやすくなり、外壁内部の腐食に繋がります。シーリングはクッションのような存在で、かつ外壁の内部を守る役割も担っています。
シーリングの劣化によるリスク
シーリングは常に紫外線や雨風にさらされているため、劣化が発生しやすいです。また、夏や冬など、季節ごとの温度変化でシーリングは伸び縮みを繰り返し、劣化が早まってしまいます。特に、寒暖差が大きい地域では、ひび割れが発生しやすいでしょう。
シーリングの劣化によってひび割れが起きたり、剥がれたりすると隙間ができてしまい、雨水の浸入を許してしまいます。隙間を放置していると、内部の腐食に加えて、カビやコケの発生に繋がります。また、外壁材の動きも大きくなってしまうため、ひび割れや剥離が発生する可能性も高くなります。シーリングの劣化を見つけたら、放置せず早めの補修が必要です。
外壁に使われるシーリングの種類
外壁に使われるシーリングは主に以下の5種類で、メリットとデメリットをまとめると以下のとおりになります。
| シーリングの種類 | メリット | デメリット |
| アクリル系 | 水性で扱いやすい | 耐久性や耐候性が低い |
| ウレタン系 | 耐久性が高く、外壁以外にも使われている | 紫外線に弱く汚れやすいため、塗装での保護が必要 |
| ポリウレタン系 | 弾力性が高く、密着性が良い | 紫外線に弱く、塗装が必要 |
| シリコン系 | 耐候性や耐水性に優れている | シーリングの上からの塗装が難しい |
| 変性シリコン系 | 塗装がしやすく、耐用年数も長い | 施工後の塗装は時間を空ける必要がある |
シーリングごとに、使用に適した場所や性能は大きく異なります。外壁に使用する場合は、変性シリコンやポリウレタンが向いています。
アクリル系
アクリル系シーリングは水性のため扱いやすく、施工もしやすいためDIYや小規模な補修に向いています。上からの塗装が可能で、外壁の色と統一した仕上がりにすることができます。紫外線や雨風の影響を受けやすく、劣化が早く進むため、小さな補修を行う際の選択肢として考えると良いでしょう。
ウレタン系
ウレタン系シーリングは弾力性があり、ひび割れしにくいのが特徴です。ただし、紫外線に弱いため、外壁に使用する場合は、塗装による保護を行わないといけません。また、表面に汚れが付きやすいため、定期的なメンテナンスも必要です。
ポリウレタン系
ゴムのような弾力性があり、密着性も高いため、コンクリートやモルタル、木材など様々な素材に使用できます。剥がれにくく、建物の動きに追従しやすいため、ひび割れが起きにくいという特徴もあります。上からの塗装も可能なので、外壁の色に合わせた仕上がりも期待できるでしょう。紫外線に弱く、屋外で使用する場合は塗装による保護を行います。
シリコン系
シリコン系シーリングは、紫外線や雨風に強く、屋外での厳しい環境に適しています。防水性も高いため、外壁だけでなく浴室やキッチンなどの水回りにも使用されています。柔軟性に優れているため、ひび割れを発生しにくいです。
ですが、シリコン系のシーリングは塗料を弾いてしまうため、上からの塗装が行えません。そのため、塗装が必要な箇所には向いておらず、使用場所を考慮する必要があります。
変性シリコン系
変性シリコン系シーリングは、シリコン系とウレタン系の特性を組み合わせた高性能なシーリング材です。塗装がしやすく、耐用年数も10〜15年と長いのが大きな特徴です。紫外線や雨風への耐性があり、長期間の保護に向いています。また、外壁や屋根、水回りなど幅広い場所で使用ができるのもメリットです。
シーリングの1液型と2液型の違い
シーリングには1液型と2液型があり、それぞれのメリット、デメリットをまとめると以下のとおりになります。
| メリット | デメリット | |
| 1液型 | 施工が簡単で、価格が安い | 耐久性は低く、定期的なメンテナンスが必要 |
| 2液型 | 耐久性や耐候性に優れている | 価格は高く、その日のうちに使い切らないといけない |
1液型
1液型シーリングは主剤のみで構成されているため、使用時に混ぜる必要がなく、そのまま使用できます。比較的簡単に施工ができるため、DIYや一般住宅のシーリング工事でよく使われています。
価格は安く、ホームセンターなどにも売られているため、手軽に入手できるのもメリットの1つです。初めてシーリング作業を行う方でも、扱いやすいです。ただし、2液型に比べて耐久性は低いため、定期的なメンテナンスが必要になるでしょう。
2液型
2液型シーリングは主剤と硬化剤の2つの成分を混ぜたもので、一般住宅以外に、ビルやマンション、工場など幅広い建物に使われています。耐久性や耐候性に優れているため、強度が求められる場所に適しています。
ただし、混ぜる手間があるため、使用までに時間がかかる点が欠点です。また、硬化も早いため、混ぜたらその日のうちに使い切らなければなりません。費用は1液型よりも高めですが、できる限りメンテナンス頻度を少なくしたい方は、2液型を検討してみましょう。
外壁のシーリングが劣化している5つのサイン
外壁のシーリングは、建物を雨水や風から守る重要な役割を持っています。ですが、常に紫外線や雨風にさらされるため、時間の経過とともに劣化していきます。シーリングの劣化を放置すると、雨漏りや外壁内部の腐食に繋がるため、劣化を見つけたら早めの補修が必要です。
シーリングのひび割れ
外壁のシーリングに細かいひび割れが入っている状態は、劣化の初期段階です。シーリングは外壁の目地を埋める役割がありますが、ひび割れがあると、雨水が浸入する隙間ができてしまいます。
ひび割れを放置してしまうと、雨漏りのリスクが高くなり、外壁内部の腐食やカビの発生に繋がります。ひび割れは比較的軽度な劣化ですが、見つけたら早めの補修がおすすめです。
剥がれ
劣化が進むと、シーリングが外壁の目地から剥がれてしまうことがあります。剥がれは、ひび割れよりも劣化が進んだ状態で、隙間も大きくなり、雨水が入り込みやすくなります。外壁内部に雨水の浸入を許してしまうため、雨漏りの原因になります。剥がれは防水性能が失われているサインでもあるため、早急な補修が必要です。
破断
シーリングの破断とは、シーリングが完全に断裂した状態です。防水性やクッションの役割が完全に失われているため、破断している場合は補修を行う必要があります。
目地に大きな亀裂が入っていたり、シーリングが完全に裂けていたりする場合は、シーリングの破断が起きているサインです。水が直接内部に浸入してしまうため、ひび割れや剥がれよりも劣化が進んでいる状態と言えます。
肉やせ
シーリングの肉やせは、シーリング自体が痩せ細った状態のことです。シーリングが縮むと隙間ができ、雨水が浸入しやすくなります。肉やせは柔軟性が失われている状態でもあるため、ひび割れや破断も起きやすいです。
肉やせが起きるのは、経年劣化により、シーリング材に含まれている柔軟性を保つ成分である「可塑剤」が溶け出し、本来の厚みが失われてしまうからです。肉やせが進行すると、隙間が大きくなるため、シーリングの剥がれに繋がることもあります。
シーリングの変色
シーリングの変色は、シーリングに含まれている可塑剤が表面に浮き出た状態です。塗料と反応したり、汚れが付着したりすることで、黒く変色する「ブリード現象」が発生します。
ブリード現象が発生している場合は、可塑剤が少なくなり、シーリング自体が硬くなっているサインでもあります。そのため、肉やせを引き起こす原因にもなります。
シーリングのブリード現象を防ぐ方法
シーリングのブリード現象を防ぐには、可塑剤を含まない「ノンブリードタイプ」のシーリングを使用しましょう。「ノンブリードタイプ」とは、シーリングに可塑剤を使用していないシーリングのことです。
ブリード現象が起こるのは、可塑剤が外部に浮き出てしまうことで発生します。可塑剤はシーリングの柔軟性を保つために使用されていますが、経年劣化によって徐々に浮き出てしまいます。汚れも付きやすく、シーリングの周囲が黒ずんだり、ベタついたりします。これにより、住宅全体の美観を損ねてしまう原因にもなります。
可塑剤を含まないノンブリードタイプのシーリングなら、可塑剤が外部へ移行しにないため、汚れもが出にくいです。外壁を綺麗に保ちたい場合は、ノンブリードタイプのシーリングを選ぶと良いでしょう。
ブリード現象が起きると、シーリング周辺の外壁が黒ずみ、見た目が悪くなるだけでなく、外壁塗装にも悪影響を及ぼします。特に白や明るい色の外壁では、黒ずみが目立ちやすくなります。
シーリングの交換や補修を検討する際は、業者に「ノンブリードタイプ」を使用するよう依頼すれば、長期間にわたって美観維持に繋がります。また、すでにブリード現象が起きている場合は、劣化が進んでいるサインでもあるため、古いシーリングを除去してから、新しいシーリングの施工を検討しましょう。
外壁シーリングの補修時期の見極め方
外壁シーリングは経年劣化などによって、ひび割れや剥がれが発生します。劣化を放置していると、雨漏りや外壁材の劣化に繋がるため、見つけたら早めの対処が必要です。使用しているシーリングによって耐用年数は異なりますが、10年程度が目安です。工事を行ってから10年ほど経過したら、専門業者への点検を依頼すると良いでしょう。
補修時期を遅らせるリスク
外壁シーリングの補修の劣化を放置すると、以下のリスクが考えられます。
- 雨漏りや水の浸入
- 外壁材の劣化
- 補修費用の増加
シーリングのひび割れは雨水が浸入しやすく、内部の断熱材や木材を腐食させる恐れがあります。また、シーリングの隙間から水分が入り込むと、外壁材の塗装が剥がれたり、ひび割れが発生する原因にもなります。
シーリングの劣化が軽度なら、補修は数万円程度で済みます。ですが、劣化が進行して、外壁の張り替えや内部の補修を行うと、より多くの費用がかかる場合があります。そのため、劣化を見つけたら点検や補修などの対策が必要です。
補修工事の進め方と注意点
補修工事の進め方は、主に以下の流れで行っていきます。
- 古いシーリングを撤去(打ち替えの場合)
- プライマーを塗布
- シーリングを充填
- 均一にならして乾燥
乾燥後の不具合が発生しないように、乾燥時間を確保できるよう天気の良い日に工事を行います。シーリングの乾燥時間は修理によって異なりますが、完全に乾燥するまでには3〜7日程度かかります。気温や湿度、季節によって乾燥時間も変わるため、シーリング補修後の管理も重要です。
補修後は定期的なメンテナンスが必要
補修が完了した後も、シーリングの状態を維持するために、定期的なメンテナンスが欠かせません。シーリングの耐用年数は10年程度ですが、シーリングの状態を3〜5年ごとに目視でチェックしてみてください。10年を目安に、専門業者への点検も検討してみましょう。
また、外壁塗装の劣化が進んでいる場合は、シーリングの補修と同時に行うことで、建物全体の耐久性向上にも繋がります。
外壁シーリングを補修する方法
外壁のシーリングを補修する際は、主に以下の2つの方法で行います。
| 補修方法 | 特徴 |
| 増し打ち | 新しいシーリングを「重ねて塗る」方法 |
| 打ち替え | 古くなったシーリングをすべて取り除いて、新しいものに入れ替える方法 |
補修方法ごとに適した状況や劣化のサインも合わせて解説していきます。
シーリングの増し打ち
増し打ちとは、既存のシーリング上から、新しいシーリングを「重ねて塗る」補修方法です。シーリングに小さなヒビが入っていたり、縮んで細くなっていたりする場合に有効な方法です。
増し打ちが必要な劣化のサインは、主に以下のとおりになります。
- 小さなひび割れ
- シーリングが少し痩せている
- シーリングの軽い剥がれが起きている
増し打ちは補修の費用が安く、工事も短期間で終わります。ただし、シーリング自体が修復されているわけではないため、打ち替えに比べて、耐久性は低めです。
また、内側や裏側の劣化に気付きにくいのが欠点でもあります。大きなひび割れやシーリングが大きく剥がれている場合は、増し打ちでの対応が難しくなってしまうでしょう。劣化が激しい場合は、「打ち替え」での補修が必要になります。
シーリングの打ち替え
打ち替えは、古くなったシーリングをすべて取り除いて、新しいものに入れ替える方法です。劣化が激しい場合の根本的な補修になるため、耐久性も高いです。
打ち替えが必要な劣化のサインは、以下のとおりになります。
- シーリングが大きく剥がれている
- シーリングがボロボロになっている
- シーリングに隙間ができている
目視でもわかるぐらいに劣化が進んでいる場合は、打ち替えを検討したほうがよいでしょう。
費用は増し打ちより高く、工事の期間も長くなりますが、外壁全体の劣化を防ぐことにも繋がります。長期的に見れば、打ち替えのほうがコストパフォーマンスが良いと言えるでしょう。
外壁シーリングの補修にかかる費用相場
外壁シーリングの補修費用の相場は、増し打ちと打ち替えで以下のとおりになります。
| 補修方法 | 費用相場(1mあたり) |
| 増し打ち | 約500円~900円 |
| 打ち替え | 約900円~1,200円 |
打ち替えの場合はシーリングの撤去も必要で、撤去費用は約1〜3万円程度かかります。また、2階以上の高所での作業には足場の設置が必要です。
足場代は住宅の大きさによって異なりますが、2階建ての戸建てでは15〜20万円程度が相場になります。平屋や工事の範囲が狭い場合は、足場の設置が不要になるため、足場代は発生しません。工事の範囲や住宅の状況によって費用は変わるため、正確な金額については、複数の業者から見積もりを取るようにしましょう。
増し打ちの費用相場
増し打ちの相場は、1mあたり500円〜900円程度になります。補修するシーリングの長さが200mの場合、費用は10万円〜18万円ほどかかります。2階建ての住宅なら、安全な作業のために足場の設置が必要です。足場代を含めると、補修全体の費用は約25〜38万円になります。
既存のシーリングの上から補修を行うため、打ち替えに比べて補修にかかる費用は安いです。工事のコストをできる限り抑えたい方におすすめと言えます。
打ち替えの費用相場
打ち替えの相場は、1mあたり900円〜1,200円程度になります。シーリングの長さが200mの場合、撤去の費用を含めると19万〜27万円ほどかかります。また、足場の設置が必要になると、補修全体の費用は34万〜47万円程度になります。
打ち替えの補修費用は増し打ちよりも高めですが、シーリングの根本的な補修になるため、耐久性に優れています。
外壁のシーリングはDIYで直せる?
外壁のシーリング補修はDIYでも可能ですが、シーリング劣化が軽度のものに限ります。たとえば、小さなひび割れや隙間が一部に発生している場合は、DIYでも補修が行えます。材料や工具を一から揃えないといけませんが、ホームセンターなどで販売されているため、比較的道具は揃えやすいでしょう。
ですが、シーリングの厚みが均等でなかったり、下地の処理が不十分だったりすると、すぐに剥がれて雨漏りの原因に繋がります。選んだシーリングが住宅周辺の環境に合っていないと、劣化が早くなる恐れもあります。
シーリング補修の失敗を最小限に抑えたい場合は、業者への依頼をおすすめします。なぜなら、専門業者なら施工の技術も高く、シーリングに関する知識が豊富だからです。業者はシーリングの補修以外にも、プライマーでの下地処理やヘラでのならし作業を行うため、均一な仕上がりにしてくれます。ホームセンターで売られているよりも、高品質なシーリングを取り扱っているため、外壁や周辺環境にあわせてシーリングを選べます。
万が一不具合が発生した場合でも、保証がついていればトラブルにも対応してもらえます。DIYの場合はすべて自己責任になるため、再補修になると余計なコストがかかってしまうでしょう。DIYの補修による不具合のリスクを考えると、業者へ依頼したほうが長期的にコストパフォーマンスが良いと言えます。
外壁シーリングの補修を依頼する際の注意点
シーリングの補修を業者に依頼する際には、適切な業者選びから、工事状況の確認、アフターフォローまで確認すべきことが多くあります。補修の依頼で失敗しないために押さえておくべき3つのポイントをご紹介します。
実績が豊富な業者を選ぶ
シーリングの補修を依頼する際は、実績が豊富な業者を選ぶようにしましょう。シーリング工事は施工の技術が仕上がりに直結するため、依頼先を間違えると劣化が早く発生することも考えられます。
信頼できる業者を見つけるには、施工事例の確認が必要です。たとえば、外壁塗装専門の業者であれば、シーリング工事も合わせて行っていることが多く、経験も豊富でしょう。自社のホームページに具体的な工事の内容や写真が掲載されていれば、業者選びの判断材料になります。
また、見積り時の説明や質問に対する対応が丁寧で、劣化の状況や工事内容をわかりやすく説明してくれる業者なら、安心して任せられるでしょう。
ただし、1社だけで決めてしまうと、工事の相場がわからず、高すぎる費用を支払ってしまう場合があります。費用をできる限り抑えるためにも、複数の会社から相見積りを取ることをおすすめします。少なくとも3社程度と相見積りを取り、価格だけでなく、材料の種類や工事内容、保証期間も比較して検討しましょう。
補修の状況を定期的に確認する
シーリングの補修工事中は、工事の進行状況を定期的に確認することが大切です。特にシーリングの打ち替えをする際は、古いシーリングの除去が適切に行われているかが重要になります。というのも、古いシーリングが残っていると、新しいシーリングの密着力が低くなり、早期の劣化に繋がるからです。
また、プライマーの塗布も確認すべきポイントです。プライマーとは、シーリング工事の下地処理に使うもので、シーリングの密着力を高める役割があります。シーリングは透明で見えにくいため、工事前に確認しておくとよいでしょう。
工事中の各工程で業者から説明を受けることも重要です。どのような材料を使用しているのか、なぜその処理が必要なのかを事前に聞いておくと、トラブル防止にもなります。工事中にわからない点があれば、その場で質問をしてみましょう。
補修後のアフターフォローについて
シーリング工事後は見た目が綺麗でも、工事中の気候や施工不良が原因で、数か月で不具合が発生する場合があります。万が一に備え、保証やアフターフォローの内容を事前に確認しておきましょう。
保証内容のチェックポイントは、主に以下のとおりになります。
- 保証期間の長さ
- 保証の適用範囲
- 定期点検の有無
- 補修対応の条件
保証期間は業者ごとに異なりますが、一般的に3年〜5年程度と言われています。保証期間内であれば、無償で補修してもらえる場合もあるでしょう。保証期間と合わせて、保証の内容も必要です。どのような不具合が対象になるのか、どの程度の劣化から対応してもらえるのかを把握しておきましょう。
また、工事後の定期点検を行っている業者もあります。定期点検によって早期の劣化に気づけるため、補修費用を抑えることに繋がります。さらに、シーリングだけでなく外壁全体を確認してもらえるため、住宅全体のメンテナンスにもなります。
まとめ
本記事では、外壁シーリングの耐用年数や劣化のサイン、補修費用の相場について解説しました。
外壁シーリングの耐用年数は約10年程度ですが、紫外線や雨風、温度変化によって、劣化が早く発生する場合があります。シーリングのひび割れや剥がれなどの劣化は、雨漏りや外壁内部の腐食に繋がるため、放置をせず早めの補修が必要です。
補修方法は「増し打ち」と「打ち替え」の2種類あり、軽度のひび割れが起きている場合は増し打ちで対応ができます。シーリングが大きく剥がれている場合は、打ち替えでの補修が必要です。愛着のある家を守るためにも、劣化が広がる前に早めの点検と補修を行いましょう。
ヒロタでは、住宅の外装診断を無料で対応しております。ひび割れやシーリングの亀裂など、気になる症状を見つけたら、WEBやお電話、LINEでお気軽にお問い合わせください。